「植物の性」と聞いて、「なにそれ?」と思う方が多いかもしれない。中学の理科の教科書では、確かに「おしべ・めしべ」を一つの花の中に持つ両性花という存在を学んだはずである。実際、植物の祖先は両性花であるが、一部の植物たちは「雄花・雌花」そして私たちヒトと同じ性染色体によって制御される「オス・メス」という形態を進化させてきた。この植物の性染色体が発見されて、今年でちょうど100年になるが、その決定分子メカニズムや進化過程は最近までほとんど知られていなかった。意外にも、これらの謎について解明の道を切り開いたのは、日本人には馴染みの深い「柿」であったのをご存じだろうか?植物の性に関する決定機構・進化メカニズム研究を国際的に先導してきた赤木剛士教授に、その研究の道のりと魅力を聞いた。
夢は音楽家だった
植物の研究者になるのは、小さい頃からの夢だったんですかと聞かれることが良くあります。でも、そんな訳ではないのです。かつて、指揮者・作曲家になることに憧れ、専門的な勉強もしていました。でも、その厳しさを目の当たりにしてプロになるのは諦めたのですが、大学に入学したらやっぱりオーケストラに熱中してしまいテストなんかそっちのけでした。研究室選びも動物実験は生理的に無理だし、植物でもイネとかシロイヌナズナとか使う王道は嫌だなあ、とかひねくれて、野菜のラボか果物のラボのどっちかかな?いや、僕はネギが苦手だから果物にしとこう、みたいな感じで果樹園芸学研究室に所属しました。音楽の方はというと、結局今でもこっそりオーケストラの指揮や依頼編曲を続けているんですけれど。

出会いは偶然
そんな折、農研機構果樹研究所で当時、ブドウの果皮色の研究をされていた小林省藏博士とお会いして、自分の研究テーマ、「柿はなぜ甘いのと渋いのがあるのか?」について議論する機会を頂きました。この機会は全くの偶然でしたが、初めて柿の研究を説明しているにもかかわらず、小林博士は未来を見透かしたかのように、その裏に潜むメカニズムを推察し、それらは実験によってすぐに実証へと至りました。ここで私の研究者としての道は決まりました。あまりに的確なアドバイス、知識と経験があればこんなことまで見えてしまうんだ!と心酔してしまったのです。こういう人が居る世界に入りたいと、それだけ考えて博士課程に進学し、研究を進めるようになりました。

新しいものにチャレンジしたい
博士課程の時の研究テーマは、「カキ果実のタンニンポリマーの蓄積に関する分子研究」でした。タンニンは渋さの原因物質です。手法としては分子生物学の枠には入っていましたが、その後、私が目指すことになるようなゲノム・集団遺伝学や進化学、ましてやバイオインフォマティクスの要素は皆無であり、液体クロマトグラフィー(HPLC)や核磁気共鳴分析(NMR)を使う機会が多いものでした。しかし、学位を取る段になり、「次は何しよう?」と悩み始めました。決してやっていた研究に飽きたわけではなく、果樹園芸学という極めて多様な作物種を扱う分野に居たせいか、いわゆる業績というものに対してそれほどシビアではない分野のせいか、とにかく新しいものにチャレンジしたいな、という気持ちが膨らんでいました。学位取得前にも関わらず、医学部の授業に忍び込んで、系統進化学だの集団遺伝学だのをかじっていたのを思い出します。
「非モデル」の柿における性決定に挑む
新しいもの、というと、私が学位取得時(2011年)、ちょうど次世代シークエンサーなる「トンデモナイ」量のゲノムやRNAの解読ができるマシンが登場してきました。バイオインフォマティクスという分野を不動の立ち位置にした技術であり、今では標準装備に近い「当世代」技術になっていますが、少なくとも私の知る限り、当時、これに長けた技術を持っていらっしゃる方は国内には少なかったと思います。
後先考えない性格なので、とりあえずプロのいそうなアメリカに行くかということで、カリフォルニア大学デービス校ゲノムセンターのLuca Comai教授のもとで日本学術振興会海外特別研究員として研究を始めました。この時のテーマは「柿の性決定因子の同定」であり、これは私が無茶言って「果樹作物しか僕はやらない」と駄々をこねた産物です。アメリカの研究所はいくつか訪ねましたが、だいたいはこの「果樹作物やりたい」で断られました。Luca Comai教授は植物における倍数性進化研究の権威の一人ですが、「何でもやるぜ!」という姿勢の方で、柿(六倍体)ゲノムの研究も許してもらえたのでした。

さて、問題は研究です。異国の地でバイオインフォマティクスの「バ」の字も知らないような奴が専門家集団に飛び込んだわけですから、当然、即座に意思疎通難民です。手取り足取りのレベルを超えて教えてくださったラボの方々には本当に感謝でした。柿は、全ゲノム情報のない「非モデル植物」と言われる存在です。ただでさえ当時は未成熟であった次世代シークエンス技術や全ゲノム解析の手法を、この難解な非モデルに使わなければならないわけです。
しかし、やってみればなんとかなるものです。ここでは、柿の二倍体野生種で雌雄異株であるマメガキのオス・メス個体のDNA配列断片をランダムに、そして大量に収集し、スーパーコンピューターパワーを最大限活用して、まるで「言葉遊び」のように、大量のゲノム配列情報の中から「オスにしか無い単語の断片」を検索するという手法を使いました。オスにしかないY染色体の断片を網羅的に集め、その言葉のパターンから重要なゲノム領域を構築するというイメージです。それだけでは性決定遺伝子までたどり着けないので、カキ属植物の進化過程と性染色体起源の情報や、雄花・雌花の構造と植物ホルモン制御の関係性を全遺伝子発現解析から考察した結果、ついに性決定遺伝子の正体が明らかになりました。留学前からこっそり始めていた進化学や集団遺伝学、博士課程の時の生化学的知見など、その全てが融合して、ようやく意味を為す結果にたどり着いた印象です。

植物の性に柿から切り込む
実は、柿(マメガキ)で性決定遺伝子が見つかった時、私はその価値に気づいていませんでした。正直なことを言うと、果樹作物の育種や栽培には詳しくても、性決定の進化やその研究の歴史に興味があまりなかったのです。しかし、論文を読み進めるうちに「まだ誰も植物で性決定遺伝子を同定していない」という事実に気づかされます。Luca Comai教授も「急げ!」とのことでしたが、そのhurry upの号令直後に彼が実施したのが遺伝子ネーミングコンテストでした。さすがイタリア人です。コンテストの結果、柿の性決定遺伝子は最終的に私の案である「Male Growth Inhibitor (MeGI:雌木) / Oppressor of MeGI (OGI:雄木)」と名付けられますが、このネーミングが、私の留学中で一番の仕事だったと自負しています。

その後、帰国して出身の京都大学農学研究科果樹園芸学研究室に助教として赴任し、柿における性決定遺伝子の発見成果を突破口として研究を広げていきました。調べれば調べるほど、植物の性決定は未知の世界であり、六倍体である柿(栽培柿)を題材にして、性の決定メカニズムや進化過程を次々と明らかにすることができました。OGIやMeGIの成り立ち、詳細な分子機作、そして性別がある野生種から「雄花・雌花」を一本の樹につける栽培柿への変化がエピジェネティック制御の違いによって成り立っている、など、他の植物たちではまだ性決定遺伝子が見つかってさえいない段階で、「非モデル」と言われた柿では研究がやりたい放題でした。
キウイフルーツと柿から紐解く「性とゲノムの進化」
柿の性決定の話ばかりしましたが、果樹園芸学の分野には他にも面白い研究対象がいくつもあって、並行して研究に取り組んできました。例えば当時で言えば、モモの栽培化、柿の果実形状の決定機構、サクラ属果樹の自家不和合性、などです。そんな折、香川大学農学部の片岡郁雄教授から「キウイフルーツも性決定あるけどやらない?」というお誘いを受けました。既に中国とニュージーランドが熾烈な争いを繰り広げていたキウイフルーツの性決定研究業界ですが、とりあえず入ってみることにしました。
この熾烈な争いは、言ってしまえば「正統派な解析データ」に基づくものでした。まだ精度は低いものの参照全ゲノム配列を解読し、膨大な分子マーカーによる高精度な遺伝地図を構築、そして変異体を作出する…どれもこれまでの遺伝学に則ったお作法通りの研究が展開されていました。この状況に真っ向勝負は不利ですし、せっかくだから新しいことをやってみたかったので、私たちは柿でうまくいった「ゲノム言葉遊び」やキウイフルーツを含むマタタビ属全体を俯瞰した進化の情報を使ってアプローチしてみました。すると、意外にも、キウイフルーツにおいても私たちが性決定遺伝子を最初に発見することができたのです。
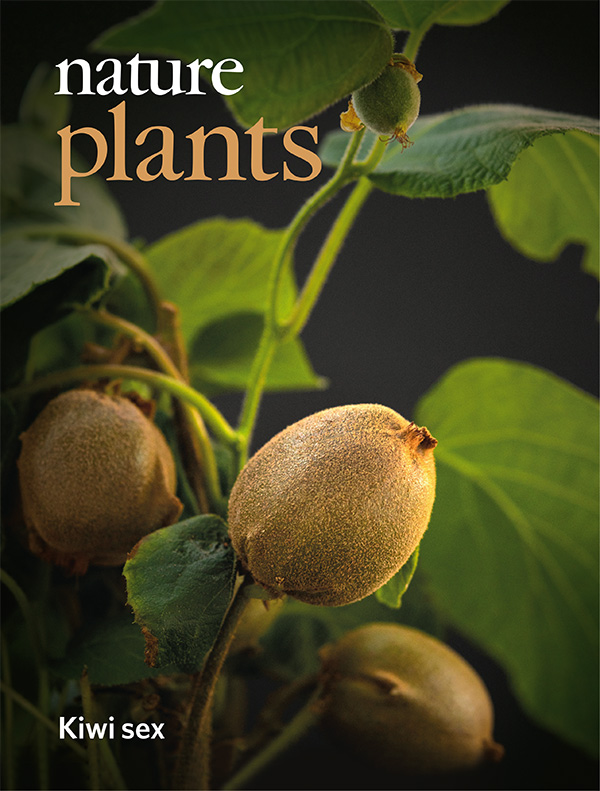
その一方、この研究の途中くらいから、植物の性決定における多様性と共通性を意識し始めるようになりました。Shy Girl(恥ずかしがり屋の女の子)・Friendly Boy(人懐っこい男の子)と名付けたキウイフルーツにおける二つの性決定遺伝子は、カキの性決定遺伝子とは全くと言っていいほど分子的な共通性のないものでした。しかし、ゲノムの進化という視点で見ると、ぼんやりとその共通点が見えてきたのです。柿もキウイフルーツも(そしてここでは紹介していない他の植物でも)「ゲノム・遺伝子重複」つまり「遺伝子が増えた」時に、性決定遺伝子が新しくできやすいことに気が付きました。これは「遺伝子重複説」と呼ばれる1970年に大野乾博士が提唱した概念の延長線にあるもので、平たく言えば「仲間が増えたら余裕ができるので新しい仕事もするよ」という、まるで人の社会の原理を映したかのような理論です。また、植物の性は一度オス・メスを作っても、また頻繁に壊れ、また新しいものを作り、と、スクラップ&ビルドを繰り返すのですが、このスクラップにもビルドにもゲノムの重複が大きな影響を与えていることが柿の研究から明らかになりました。

理論研究もAIも、社会実装も
今は、この「植物における性の進化」の共通原理の探索を続けており、扱う植物も増えてホップやヒロハノマンテマなども研究対象になりました。といっても、未だにどれも「園芸植物」でして、どうにも「食べられない」「人の役にたたない」植物には興味が湧かないのです。ホップは農学部的には果樹作物に入りますが、ヒロハノマンテマはイングリッシュガーデンなどに咲いている北ヨーロッパの花ですね。今からちょうど100年前、1923年に初めて被子植物で性染色体が発見されたのが、この「ヒロハノマンテマ」と「ホップ」(あと「スイバ」)です。なので、研究内容も性染色体進化の理論研究に広がりを見せ、そのおかげで、いわゆる理論進化の世界的大御所たちと繋がりを持つことができ、新しい世界を体験させて頂いています。

研究内容は性決定だけでなく、果実の形状多様性や成熟機構のメカニズム解明、400年もクローン繁殖を続けている(遺伝的には一種一個体の)ウンシュウミカンのゲノム構造進化、あと、趣味?が高じて始めたAI技術の活用なんかもあります。AI研究は、画像・ゲノム配列・RNA情報など、なんでも相性が良く、性決定研究にも使っていますが、遺伝子という存在が一切出てこない農業現場での「選果(収穫後の選別)」や「人の嗜好性判別」みたいな、完全に社会実装目当ての開発も取り組んでおり、これが非常に楽しいのです。AI研究は、九州大学システム情報科学研究院の内田誠一先生という、完全に情報の世界の方に弟子入りして始めたものですが、これも、為せば成るというか、とりあえず飛び込んで本気でやれば何とかなるものです。学生も、農学部ですから情報学の知識ゼロでラボに入ってきますが、数か月もすれば、私が見たこともないコードを勝手に扱っていたりして、ホントに成長の可能性は無限大だと感じています。

最後に、私自身、まだまだ若手を自負しているつもりですが、この短い道のりにおいてさえ、とにかく「たくさんの人との出会い」がターニングポイントとなっています。ここまで何人かの先生のお名前を挙げさせて頂きましたが、その度に、新しい世界を見せて頂き、インスパイアされて研究を続けて来れました。更なる若手に何か伝えることがあるとすれば「出会いを大切に」ですかね?
構成協力/撮影 松林 嘉克
赤木 剛士 プロフィール:
2006年 京都大学農学部卒業。京都大学大学院農学研究科にて博士(農学)の学位を取得。2011年 京都大学白眉プロジェクト特定助教、京都大学農学研究科助教、2019年より岡山大学環境生命科学研究科准教授、研究教授を経て2023年より現職。